活動報告 - 最新エントリー
中央大学学員会 東京杉並区支部 平成24年度第10回 幹事会議事録
平成25年3月29日
総務委員長 中田 久尚
日 時: 平成25年3月18日(月)午後6時30分―午後8時
場 所: 阿佐ヶ谷地域区民センター 出席者: 15名
進 行: 與川幹事長
支部長挨拶: 3月23日に大学評議員会開催。山手学院、久野氏関連問題が議題
に。3月末、都区内支部幹事を25年度目黒幹事支部へ引き継ぎ。
報告事項(各委員長、各地区・同好会担当者)
・中田総務委員長:前回の幹事会議事録と今後の行事予定(来年度6/29支部
総会・各地区会等)の案内。
・片山事業委員長:平成25年度学術講演会テーマ第一希望「中国政治体制100
年」・深町英夫氏、第二希望「『アベノミクス』と日銀の金
融 政策」・建部正義氏に決定し学員会へ申請。日時は新体
制が決定する。
・山下会計委員長:1/31現在52名だったが督促結果、18名納付。残りの未納者に再
度3月2・3日と9日に督促。現在、取りまとめ中。
・中田ゴルフ同好会:5月中、中野支部他隣接支部との合同ゴルフ大会を計画。
11月に第24回白門ゴルフ大会実施予定。
・安西俳句同好会長代理:3/9月例句会。兼題は「春場所・春の雪」
4月例会は4/13久我山会館で。兼題は「浅蜊・辛夷(こ
ぶし)」
・本田グルメ同好会長:次回グルメ会は4/22(月)午後5時〜7時
イタリア料理店「ラ・ヴォーリア・マッタ」
荻窪ルミネ5F
*次回25年度第1回幹事会は4月16日(火)午後6時30分より
於阿佐ヶ谷地域区民センター
平成25年3月29日
総務委員長 中田 久尚
日 時: 平成25年3月18日(月)午後6時30分―午後8時
場 所: 阿佐ヶ谷地域区民センター 出席者: 15名
進 行: 與川幹事長
支部長挨拶: 3月23日に大学評議員会開催。山手学院、久野氏関連問題が議題
に。3月末、都区内支部幹事を25年度目黒幹事支部へ引き継ぎ。
報告事項(各委員長、各地区・同好会担当者)
・中田総務委員長:前回の幹事会議事録と今後の行事予定(来年度6/29支部
総会・各地区会等)の案内。
・片山事業委員長:平成25年度学術講演会テーマ第一希望「中国政治体制100
年」・深町英夫氏、第二希望「『アベノミクス』と日銀の金
融 政策」・建部正義氏に決定し学員会へ申請。日時は新体
制が決定する。
・山下会計委員長:1/31現在52名だったが督促結果、18名納付。残りの未納者に再
度3月2・3日と9日に督促。現在、取りまとめ中。
・中田ゴルフ同好会:5月中、中野支部他隣接支部との合同ゴルフ大会を計画。
11月に第24回白門ゴルフ大会実施予定。
・安西俳句同好会長代理:3/9月例句会。兼題は「春場所・春の雪」
4月例会は4/13久我山会館で。兼題は「浅蜊・辛夷(こ
ぶし)」
・本田グルメ同好会長:次回グルメ会は4/22(月)午後5時〜7時
イタリア料理店「ラ・ヴォーリア・マッタ」
荻窪ルミネ5F
*次回25年度第1回幹事会は4月16日(火)午後6時30分より
於阿佐ヶ谷地域区民センター
京王・井の頭沿線地区会では、14名が集まり、3月30日に恒例の「お花見会」を開催しました。
午後1時に、大宮八幡宮の前に集合し、大宮和田掘公園を散策しました。
 今年の開花は3月16日と早く、22日には
今年の開花は3月16日と早く、22日には
満開となってしまいましたが、その後しばら
く冷え込んだ為か、まだ花は残っており、そ
の淡い美しさを周囲に漂わせていました。


雨も上がり暖かくなることを期待しましたが、冷え込みました。
そこで道すがら、いつもの釣り掘り食堂で暖を取り、しばし室内からの花見です。



2時30分には、懇親会場の「びっくり寿司」に到着しました。
あとは心行くままに、話しの花が咲きまくりました。
高嶋支部長からは近況のご報告があり、中大野球部の個人応援団長・斉藤さんからは、今年も球場へ応援に行きましょうと、熱いお誘いを受けました。
花はどこにでも咲くものです。


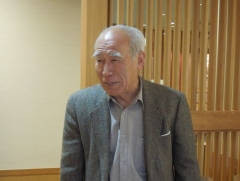

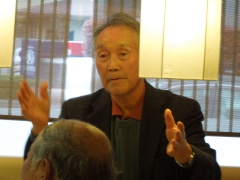

また来年お会いしましょう。
--
午後1時に、大宮八幡宮の前に集合し、大宮和田掘公園を散策しました。
 今年の開花は3月16日と早く、22日には
今年の開花は3月16日と早く、22日には満開となってしまいましたが、その後しばら
く冷え込んだ為か、まだ花は残っており、そ
の淡い美しさを周囲に漂わせていました。


雨も上がり暖かくなることを期待しましたが、冷え込みました。
そこで道すがら、いつもの釣り掘り食堂で暖を取り、しばし室内からの花見です。



2時30分には、懇親会場の「びっくり寿司」に到着しました。
あとは心行くままに、話しの花が咲きまくりました。
高嶋支部長からは近況のご報告があり、中大野球部の個人応援団長・斉藤さんからは、今年も球場へ応援に行きましょうと、熱いお誘いを受けました。
花はどこにでも咲くものです。


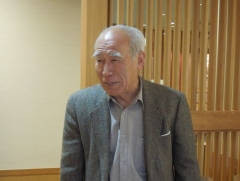

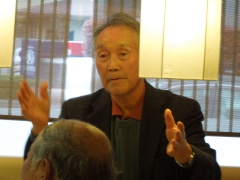

また来年お会いしましょう。
--
◆句会は原則として毎月第二土曜日の午後1時半から4時位まで、主として久我山会館・高井戸地域区民センター等で開催しております。(出席者は10名程度)一度ふらっと覗いてみて下さい。その上で、ぜひ仲間になって下さい。
句会が終わると駅前の蕎麦屋でちょこっとやったりもします。
◆毎回、その月の作品を紹介いたします。
・3月の作品の紹介
・3月の兼題は、「春場所」・「春の雪」です。
俵木 陶光
・春場所や今も大鵬手に賜杯
山口 月山
・春場所や難波の空へふれ太鼓
岡村 一道
・春の雪東京は坂多き街
長岡 帰山
・かりそめのわが影を置く春の雪
峯岸 まこと
・湯の街の濡れて融けゆく春の雪
安西 円覚
・ひとことも発せず消えし春の雪
片山 朝陽
・石垣のすき間に消えし春の雪
五井 夢
・現世(うつつよ)はきまぐれ心春の雪
中邑 雅子
・降り積もる結願(けちがん)の日の春の雪
小林 美絵子
・風光るホームに電車待つ五分
芳村 翡翠
・春の雪昏れゆく海に溶け入りぬ
肥田 浩一
・水墨の春の雪降る立石寺
堀 秀堂
・春雪の戯れし夜の明けにけり
浦田 久
・陽光に乱反射する春の雪
◆ 『郷愁の詩人 与謝 蕪村』 を読んで
(萩原 朔太郎著)昭和11年刊
安西 円覚
2月の本稿で陶光先生が「蕪村」を取り上げられましたので「蕪村」入門書として最適と言われる本書を読んでみました。
遅き日のつもりて遠き昔かな 蕪村
(春の日の暮れるまで遅々としている日永(ひなが)の日々が、幾重にも積もって遠き昔に繋がっている)
日本近代詩の父といわれる萩原朔太郎はこの句を、蕪村の代表俳句として挙げ、「蕪村のポエジー(詩)の実体は、時間の遠い彼岸に実在している彼の魂の故郷に対する《郷愁》であり、昔々しきりに思ふ子守唄の哀切な思慕であった。」と、一貫してこの言葉をリフレインし、また「青春性・浪漫性・洋画風」などの語が文章のあちこちに散りばめられています。
枯淡とか寂び、風流という一般的特色と考えられている俳句を毛嫌いしていた朔太郎にとって唯一の例外として蕪村の俳句だけは好きでありました。そこに明治以後の詩壇における欧風の若い詩とも情趣に共通するものを感じ取っていたからです。
一方、彼は、正岡子規の蕪村論に強烈に反論をしています。子規とその門下生の根岸派一派の俳人は自然をその「あるがままの印象」で単に平面的にスケッチする「写生主義」を当時唱えていた。そして蕪村こそがかれらの写生主義にマッチした規範的俳人とみなされていた。朔太郎は、蕪村が単なる写生主義者ではなくその句に情感が深く描かれ、郷愁が痛切にうたわれている真の叙情詩人であると主張する。
このように本書では朔太郎は新しい詩人の鑑賞眼で古典俳句のリリック(抒情詩)の真の詩的精神を見直そうとしたのです。
蕪村に関しては小生は”菜の花や月は東に日は西に”におけるように、色彩感覚がすぐれている句を作る、また画家の眼から作句してる人だな〜と十代の頃から感じていました。最近、近代・現代の俳句ばかり目にしていましたが、今回古典俳句に関するこの評論を読みまして古典俳句をより身近に感じ、もっともっと見直さなければと感じています。
◆次回の句会は、4月13日(土)1時半より4時半
会場は、久我山会館です。
兼題は、「浅蜊」・「辛夷(こぶし)」です。
◆句会についてのお問い合わせ先: 片山 惠夫(俳句会事務局長)まで
TEL 090−8773−4881
◆文責・俳句同好会会長 俵木 敏光(陶光)
京王・井の頭沿線地区会 会員各位
京王・井の頭沿線地区会では、
平成25年
2月 2日:平成24年度 第6回役員会
3月 2日:平成24年度 第7回役員会
3月16日:平成24年度 第8回役員会
をそれぞれ開催いたしました。
内容は、
1)3月30日の花見会について/日程、内容、会費、案内方法、次第と運営分担など
2)秋の第10回総会時での記念品等の取扱いについて/実施するか、実施する場合の内容、対象、予算など。 この件については、お花見会の案内時にアンケートを実施して、会員諸氏のご意見ご希望を伺うことにしました。
3)秋の役員任期切れについて
でした。
以上、遅くなりましたが、まとめてご報告申し上げます。
--
京王・井の頭沿線地区会では、
平成25年
2月 2日:平成24年度 第6回役員会
3月 2日:平成24年度 第7回役員会
3月16日:平成24年度 第8回役員会
をそれぞれ開催いたしました。
内容は、
1)3月30日の花見会について/日程、内容、会費、案内方法、次第と運営分担など
2)秋の第10回総会時での記念品等の取扱いについて/実施するか、実施する場合の内容、対象、予算など。 この件については、お花見会の案内時にアンケートを実施して、会員諸氏のご意見ご希望を伺うことにしました。
3)秋の役員任期切れについて
でした。
以上、遅くなりましたが、まとめてご報告申し上げます。
--
央大学学員会 東京杉並区支部 平成24年度第9回 幹事会議事録
平成25年2月28日
総務委員長 中田 久尚
日 時: 平成25年2月18日(月)午後6時30分―午後8時
場 所: 産業商工会館 出席者: 19名
進 行: 與川幹事長
支部長挨拶: 1/14・15の俵木前支部長御内室の葬儀のお手伝い有難うございました。1/26「グルメ会」世話役の方、有難うございました。
6月の定期総会への準備につきまして、ご支援とご協力をお願いします。
報告事項 (各委員長、各地区・同好会担当者)
・中田総務委員長:前回の幹事会議事録と今後の行事予定(来年度6/29支部
総会・各地区会等)の案内。
・片山事業委員長:全国支部長会議・定時協議員会・定時学員総会開催日時の案
内。25年度の学術講演会「講演者・講演テーマ・講演概要が
2/20前後に決まる。平成24・25年度同好会事業報告・決算・
予算提出書配布。片男波部屋情報。
・山下会計委員長:会費の銀行引落としの提案。地区会よりの会費請求は効果有
り。総会の会費の減額の提案。
・井原組織委員長:会員異動報告。退会1名。来年度の地区会・同好会への助成金
は3万円に決定。(支部長承認)
・富田ボランティア委員長: 法律・税金セミナー、クリーンデー25年度も。
・増田ハイキング同好会長:4月下旬実施予定。
・富田旅行同好会長:旅行先は25年度秋、福島県飯坂温泉が有力。
・木村カラオケ同好会長:月例会は第二月曜日。「ボーンワールド」にて。
・中田ゴルフ同好会:5月頃、中野支部他隣接支部との合同ゴルフ大会を計画。
・安西俳句同好会長代理:2/9月例句会。兼題は「余寒・バレンタインデー」
3月例会は3/9高井戸地域区民センターで。兼題は「春場
所・春の雪」
・本田グルメ同好会長:2/26グルメ会13名参加。4月中旬イタリア料理を予定。
*なお、当支部岡田茂副幹事長が24年度杉並区功労表彰者に選ばれました。
出席者全員で祝福しました。
*次回幹事会は3月18日午後6時30分より午後8時 於阿佐ヶ谷地域区民センター
平成25年2月28日
総務委員長 中田 久尚
日 時: 平成25年2月18日(月)午後6時30分―午後8時
場 所: 産業商工会館 出席者: 19名
進 行: 與川幹事長
支部長挨拶: 1/14・15の俵木前支部長御内室の葬儀のお手伝い有難うございました。1/26「グルメ会」世話役の方、有難うございました。
6月の定期総会への準備につきまして、ご支援とご協力をお願いします。
報告事項 (各委員長、各地区・同好会担当者)
・中田総務委員長:前回の幹事会議事録と今後の行事予定(来年度6/29支部
総会・各地区会等)の案内。
・片山事業委員長:全国支部長会議・定時協議員会・定時学員総会開催日時の案
内。25年度の学術講演会「講演者・講演テーマ・講演概要が
2/20前後に決まる。平成24・25年度同好会事業報告・決算・
予算提出書配布。片男波部屋情報。
・山下会計委員長:会費の銀行引落としの提案。地区会よりの会費請求は効果有
り。総会の会費の減額の提案。
・井原組織委員長:会員異動報告。退会1名。来年度の地区会・同好会への助成金
は3万円に決定。(支部長承認)
・富田ボランティア委員長: 法律・税金セミナー、クリーンデー25年度も。
・増田ハイキング同好会長:4月下旬実施予定。
・富田旅行同好会長:旅行先は25年度秋、福島県飯坂温泉が有力。
・木村カラオケ同好会長:月例会は第二月曜日。「ボーンワールド」にて。
・中田ゴルフ同好会:5月頃、中野支部他隣接支部との合同ゴルフ大会を計画。
・安西俳句同好会長代理:2/9月例句会。兼題は「余寒・バレンタインデー」
3月例会は3/9高井戸地域区民センターで。兼題は「春場
所・春の雪」
・本田グルメ同好会長:2/26グルメ会13名参加。4月中旬イタリア料理を予定。
*なお、当支部岡田茂副幹事長が24年度杉並区功労表彰者に選ばれました。
出席者全員で祝福しました。
*次回幹事会は3月18日午後6時30分より午後8時 於阿佐ヶ谷地域区民センター
